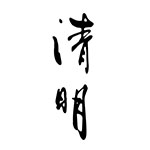大寒
大寒の一戸もかくれなき故郷 飯田 龍太
二十四節気の中でも、大寒はよく知られています。天気予報士がテレビで「今日は大寒です」と言うと、一段と寒さを感じて身が引き締まるような気がします。2018年の大寒は1月20日でした。
この句は大寒の代表的な句です。作者の飯田龍太は高名な俳人だった飯田蛇笏の息子で、山梨県の笛吹市に住んでいました。四男でしたが、3人の兄が戦死や戦病死したため、家を継ぎ、父の俳誌「雲母」も継承しました。四男でありながら、家を継ぐことになった龍太。覚悟を決めて数年後、33歳の作です。親子が住んだ家は甲府の東南、御坂山系につづくゆるやかな丘陵の中ほどに、今もあります。そこからは甲府盆地が眺められ、空気の澄みきった日には南アルプスが望めます。
木々が落葉して何ものにも邪魔されない冬は家々がよく見えたのでしょう。「一戸もかくれなき」という徹底した表現が大寒に合っています。
大寒は寒さが極まる日ですが、力強い響きのある言葉です。

薬喰
薬喰女揃うて黒づくめ 三木 瑞木
現代は毎日のように肉料理を食べますが、わが国では仏教が伝来してから獣肉を食べることが敬遠されていました。特に江戸時代の生類憐みの令の後は食されなくなったようです。それでも、獣肉は栄養価が高いので、身体が弱っている人には特に食べさせたいですし、美味しいことは分かっていました。そこで、「薬の代わり」と言う理由をつけて、狩猟した鹿肉や猪肉を食べました。今で言うジビエです。特に冬は血行を良くするので、寒さを乗り切るために食べたようです。それが冬の季語「薬喰」です。
この句は薬喰と称して、猪肉の牡丹鍋か鹿肉の紅葉鍋を食べたのでしょう。女性達が集まったところ、誰もが皆、黒を着ていたのです。黒はお洒落な色ですが、薬喰だけに、世間の目を憚って黒を着込んできたようにも見えて面白いと思ったのでしょう。
なかなかに勇敢でパワーのある女性陣だったのではないでしょうか。

臘梅
臘梅や人待つならば死ぬるまで 藺草 慶子
臘梅(または蠟梅)は12月から2月頃に咲くロウバイ科の落葉低木です。まだ葉を出さないうちに黄色い小さい花が枝に出て、梅のような香りを放ちます。光沢のある花に気品がある上、芳香が良いのでファンが多い花です。
この句には少し驚かされました。「死ぬるまで」という言葉が強いですね。人生百年だとしても、そこまで待ちます、とはなかなか言いきれません。
「人待つならば」という言い方からは、特定の誰かが振り向いてくれるのを待っているとも受け取れますが、誰かいい人が現われるのを待っているとも受け取れます。一生を賭けて人を愛したい、そういう人に巡り合いたいという願望ではないでしょうか。
臘梅の香と艶が、永遠の恋人を待つ心に通じていて魅力があります。