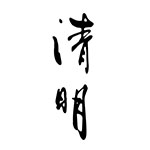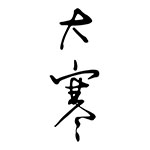短夜
短夜の青嶺ばかりがのこりけり 加藤 楸邨
「短夜」は日の入りから日の出までの時間が短い夏の夜のことです。「明易し」とも言い換えられる季語です。
夏の短い夜が明けてしまうのを惜しむ気持ちが託されているのですが、そこには後朝(きぬぎぬ)の思いも籠められています。後朝は平安時代、通い婚だったころに、男性が女性の家に行って一夜を共にした翌朝、別れることを意味しました。
でもこの句は男女のこととは全く違う内容で、清々しさのある句です。夏の夜、灯りが消えた窓の外を見ると、稜線が青く残って見えていたのでしょう。そればかりでなく、寝床に入って瞼を閉じると、昼間見た緑の濃い山々が瞼に浮かんできて寝つかれないのです。
夏の夜に山小屋で寝ていて心まで青く染まっていたのかもしれません。青い山に囲まれて、自然と一体になって眠る時の充実感が若々しく詠まれています。

カメラ片手の山歩記様のサイトから画像をお借りしました。
ありがとうございます。
梅漬
梅漬けて煮ていちにちを使ひきる 村上 喜代子
「梅干」は一年中食べることができますが、梅を漬けるのが夏なので歳時記では夏の季語になっています。さらに「梅漬」「梅干す」「梅筵」等、梅干を作ることに纏わる言葉も季語です。
梅干を作るのは六月の半ば過ぎですね。先ず、容器や重石を殺菌し、青梅を洗って、ヘタを楊枝で一つずつ取って、塩と梅を交互に敷き、落し蓋と重石を載せたら、この日の梅漬の作業は完了です。数日後に紫蘇を入れ、土用の頃、天干しします。この作者はその日、煮梅も作りました。青梅にシロップを含ませてゆっくり煮ます。そうしたらその日いちにちが終わってしまったというのです。でも充実した一日だったのでしょう。その思いが「使ひきる」に表われています。
黙々とした作業ですが、家族の健康の源になる梅干と煮梅を仕込んで安堵した一日。梅雨の間でも、こんな風に過ごす日があるのはいいものですね。

蛍袋
逢ひたくて螢袋に灯をともす 岩淵 喜代子
釣鐘草とも呼ばれる蛍袋が道端に咲く頃となりました。色は淡紅や淡紫や白がありますが、どれも静かな風情で、寂しそうで、人恋しさを感じさせます。俳句では、その中に何かを入れてみたり、うつむいた姿を何かに見立ててみたり、さまざまな試みがなされ、例句もたくさんあります。
この句はその風情から思い切って「逢ひたくて」が導きだされました。「逢」は「逢瀬」の意味があるので、この句は恋の句です。作者は恋い焦がれても逢えない相手を迎えるために、蛍袋に灯をともしたというのです。その灯りを目印に、恋人が訪ねてきて欲しいという思い。ロマンティックですね。
控えめな花に託された恋は、きっと深い愛に変わってゆくのでしょう。