「 季語でつなぐ日々 」 一覧
-

-
2018/05/11 -季語でつなぐ日々
五月 緑の台地わが光背をなす五月 金子 兜太 今年の2月20日、98歳で亡くなった金子兜太さんの、30代の作です。金子兜太さんは戦後の俳壇を率いてきた大きな存在でしたから、訃報はニュースに …
-

-
2018/04/23 -季語でつなぐ日々
穀雨 裏木戸に穀雨の日差ありにけり 角田 独峰 穀雨(こくう)は穀物を育てる雨という意味で、二十四節気の一つです。2018年は4月20日でした。あまり知られていない二十四節気ですが、早苗が育つ頃 …
-
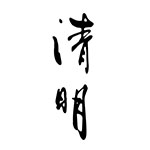
-
2018/04/06 -季語でつなぐ日々
清明 清明やきらりきらりと遠き鍬 大橋 弘子 清明は「清浄明潔」の略です。その文字の通り、空気が澄んで陽光が明るく、万物を鮮やかに照らしだすという意味の二十四節気です。この時期になると、萌え出た …
-

-
2018/03/26 -季語でつなぐ日々
春分 春分の田の涯にある雪の寺 皆川 盤水 春分も二十四節気の一つです。太陽が春分点を通過する時刻が春分ですが、その時刻がある日を暦で春分と呼んでいます。今年は3月21日でした。この日はお彼岸の中 …
-
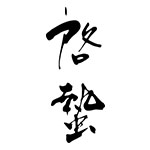
-
2018/03/07 -季語でつなぐ日々
啓蟄 啓蟄の上野駅から始まりぬ 鈴木 只人 3月6日は二十四節気の啓蟄でした。啓蟄の「啓」の字には「戸」と「口」があります。口を開けるように戸を開くという意味の字です。「蟄」の字は、蟄居というとき …
-

-
2018/02/22 -季語でつなぐ日々
雨水 低く出づ雨水の月のたまご色 岸 さなえ 二十四節気の一つ雨水は「うすい」と読みます。立春が過ぎて厳しい寒さが遠のき、空から降るものが雪から雨になり、氷が溶けて水になる頃という意味で、今年は2 …
-

-
2018/02/06 -季語でつなぐ日々
立春 肩幅に拭きゆく畳春立ちぬ 小西 道子 春の最初の二十四節気は立春。「春立つ」とも言います。今年は2月4日でした。「暦の上では春になりましたが」という言葉がよく使われる通り、立春を迎えたと言っ …
-
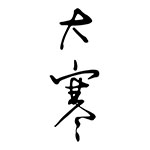
-
2018/01/25 -季語でつなぐ日々
大寒 大寒の一戸もかくれなき故郷 飯田 龍太 二十四節気の中でも、大寒はよく知られています。天気予報士がテレビで「今日は大寒です」と言うと、一段と寒さを感じて身が引き締まるような気がします。201 …
-

-
2018/01/10 -季語でつなぐ日々
小寒 小寒や楠匂はせて彫師なる 坪野 文子 小寒は1月の初めの二十四節気で、今年は1月5日。この日から節分までが「寒」です。 したがって、小寒の日を「寒の入り」、15日後の1月20日を「大寒」、 …
-

-
2017/12/25 -季語でつなぐ日々
冬至 玲瓏とわが町わたる冬至の日 深見 けん二 冬至はよく知られている二十四節気です。北半球で、正午の太陽の高度が一年中でもっとも低くなり、昼がもっとも短くなる日です。今年の冬至は12月22日です …
-
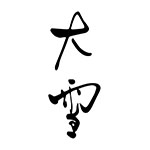
-
2017/12/08 -季語でつなぐ日々
大雪 大雪や束なす朝日畑を射る 菅野 トモ子 大雪は二十四節気の一つで、「たいせつ」と読みます。「おおゆき」と読むと大量の降雪の意味になってしまいます。 今年の大雪は12月7日。山間部だけでなく …
-

-
2017/11/22 -季語でつなぐ日々
小雪 小雪や声ほそほそと鳥過ぐる 鍵和田 秞子 小雪は、立冬から十五日後、雪が降り始める頃という意味を持つ二十四節気です。地域によっても異なりますが、雪がまだ降っていない土地にも、山間部の雪の …
-

-
2017/11/07 -季語でつなぐ日々
立冬 立冬のことに草木のかがやける 沢木 欣一 立冬は冬に入ったという意味の二十四節気です。今年は11月7日が立冬です。 季語では「冬立つ」「冬に入る」「冬来る」などとも使われますが、言葉によっ …
-

-
2017/10/24 -季語でつなぐ日々
霜降 霜降やスリッパ厚く厨事 井沢 正江 霜降(そうこう)は文字通り、霜が降りはじめるという意味の二十四節気です。今年は10月23日に当たります。秋がいよいよ深くなって、大気が澄み、野山の紅葉も濃 …
-

-
2017/10/10 -季語でつなぐ日々
寒露 投網打つ男翳濃き寒露かな 竹村 完二 寒露は露が寒さで凝結して氷るようになるという意味の二十四節気ですが、実際に霜が降りるのはもう少し先です。 空気が少しひんやりと感じ始めて、空も水も透明 …




