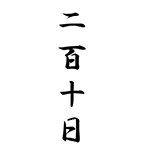文/石地 まゆみ
葵祭
行列に風の寄り添ふ懸葵 西宮 舞
京都の下鴨神社、上賀茂神社の例祭は葵祭、正式には賀茂祭といい、祇園祭、時代祭と並ぶ京都三大祭りの一つとして知られています。また、石清水祭・春日祭とともに、三大勅祭(天皇の使者である勅使が遣わされる祭礼)でもあります。5月15日の平安絵巻さながらの行列は有名ですね。江戸時代から、祭りに二葉葵の葉を装飾に使うようになって、葵祭と呼ばれるようになったそうです。「懸葵(かけあおい)」も季語となっています。
その起源は今から約1500年も前。6世紀の欽明天皇の時代に、天候不順が長く続き大凶作となり、占いをすると賀茂の大神の祟りだということが分かりました。そこで賀茂神の祭礼をし、五穀豊穣を祈ったのです。祟りや怨霊が起源となっている行事が多々ありますが、この優雅な祭も、もとは祟りしずめだったのですね。賀茂神社と朝廷の行事でしたが、御所から神社までのきらびやかな行列は、平安時代も貴族がこぞって見物に出掛けました。『源氏物語』でも、葵の上と六条御息所の車争いの場面が出てきますが、その頃からこの祭の人気と人出の多さが分かります。
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

賀茂街道を行く葵祭の行列。路頭の儀。御所から上賀茂神社。
15日の行列は「路頭の儀(ろとうのぎ)」といわれて、御所から下鴨神社・上賀茂神社へと参詣に向かうもので、斎王や勅使を中心に検非違使(けびいし)、牛車、風流傘、舞人たちが、馬に乗り、輿を曳き、長い列を作って8kmの道のりを進んで行きます。
作者は5月の薫風の中で、その祭行列を見ています。平安朝の装束の、総勢500名の列が、雅にしずしずと、進んで行きます。平安時代は「祭」といえばこの賀茂祭のことで、俳句で「祭」が夏の季語となったのも、この祭からなのだ、と感慨深く見ています。先に書いたように、供奉する人々の挿頭(かざし)、牛車のすだれには、「懸葵」といわれる二葉葵の緑の葉が揺れています。日に照らされさらに輝くような行列に、やさしい風が吹いていきます。行列の進む先を、後を、寄り添うように吹く風が、作者の頬も撫でてゆきます。作者も平安の世にいるような錯覚に陥ったことでしょう。
ただ、賀茂祭はこの15日の行事だけではありません。上賀茂、下鴨神社では、5月1日から競馬会足汰式(くらべまえあしぞろえしき)、流鏑馬神事(やぶさめしんじ)、斎王代禊の儀(さいおうだいみそぎのぎ)、歩射神事(ぶしゃしんじ)、賀茂競馬(かもくらべうま)。そして12日に下鴨神社では御蔭(みかげ)祭、上賀茂神社では御阿礼(みあれ)祭が行われます。これは神霊を迎える重要な儀式で、それぞれの神社の神霊が生まれ変わり、新しい力を備えられるという神事です。秘儀ですから、見ることはできませんが。
新しくよみがえった神霊が、葵祭の行列を、見守っています。
立砂の全き葵祭かな まゆみ
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

葵祭には、二葉葵と桂を組み合わせた「葵桂」が飾られる。
御簾や勅使、牛馬まで、この日に使われる葵の葉は1万枚に上るという。

上賀茂神社の細殿。シャープに尖った円錐形の立砂が一対。ご祭神が降臨された神山にちなむもので、一種の神籬である。
袋掛
庭先のすこしのものに袋掛 下村 梅子
桃、梨、葡萄、林檎。花時が終わって、少しずつ、小さな実を育て始めました。その果実を病気や、虫、鳥の害、風害から守るために紙袋をかぶせる作業を、袋掛といいます。日焼けや葉擦れ、枝擦れなども防いで、見た目をよくするためにも必要です。これは日本独特の技術で、明治時代に始まったのだとか。たくさん実が付くと、栄養がすべてに回らないので、余分な実を摘む摘果という作業をしますが、これと同時にすることが多いようです。作業の効率のためでしょう。
実の一つ一つに、林檎や桃なら脚立に乗って袋を掛けます。葡萄だったら、葡萄棚で身をかがめながらの作業です。夏の日差しを浴びての大変なご苦労ですが、消費者に少しでもきれいな美味しい果実を食べてもらいたい、という農家の方の思いと丁寧な作業によって、果実は私たちの元に届けられるのです。
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

梨の袋掛。緑の葉の中の掛けた白い袋は、熟すのを待つ楽しみである。
果樹園で、緑の中に白い紙袋が何百も掛けられた光景。これからの収穫の楽しみでもあり、白い袋が風に鳴る様子、実が育って甘い香りを放ちながら弾けそうな様子、どちらも、夏の美しい景です。
作者は庭で、ほんの少し、家族で食べる程度の果実を育てています。たくさんではないけれど、やっぱり美味しい、きれいな実を育てたい。そんな気持ちで、袋掛けをしました。すこしのものに、少しの手間ですが、作者にとっては大切で、楽しみでもあります。掛け終わって、あとは健やかに育ってくれるのを待つばかり。たしかにこんなふうに、庭や玄関先の果実に袋掛けをしてある家を見かけます。ほほえましいものです。
袋掛終へて羽州の日照雨かな まゆみ
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

実が大きくなるまでは、空気に包まれているよう。
右は葡萄。この写真は9月になって、すでに袋から実がはちきれそうに覗く。
麦
麦の穂の焦がるるなかの流離かな 森 澄雄
九州の高速バスに乗っていたら、濃い黄金色のじゅうたんが見えました。遠い連山へと、ただただ広がる黄色。なんだろう?と目を凝らすと、それは広大な麦畑でした。
日々の生活に欠かせない麦。初冬に蒔かれた麦は、根張りをよくする冬の麦踏に強くなり、春に青々と育って、やがて黄色く熟していきます。青麦も美しいものですが、新緑の中での黄色の穂は、圧倒される迫力を持っています。
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

知らなかったが、筑後川流域は麦の産地として有名だった。北海道に次いで福岡県は全国2位だという。
麦は種類が色々とありますが、ユーラシア地方では約1万年も前には栽培が始まったといいますから、その歴史はとてつもなく古いものです。中国経由でやってきた日本でも、2千年前の遺跡から発見されているのだそうです。記紀にも、大地の女神から五穀が生まれたという穀物神話の中に、麦も出てきます。スサノオがオオゲツヒメを殺してしまった時、その陰(ほと、女性器)から生ったのが麦であると。「陰に生る麦尊けれ青山河 佐藤鬼房」の句の背景にも、その神話が心にあったのでしょう。「麦の穂」「麦刈る」「麦の秋」と平安時代の和歌にも出てきています。
筆者が見たのは、栽培の産地の一つ、福岡の筑後川流域だったのでした。そこは、南朝後醍醐天皇の皇子・懐良(かねなが)親王が征西将軍として九州に赴き、転戦を重ねた場所でした。南朝びいきの筆者は、その時代に思いを馳せていた時に出逢った、熟れた麦の色が広がる景でした。
この句の作者も、麦の穂波を見ながら、流離の心を抱いています。「焦がるる」は、「火に焼けたよう」に燃えるような熟れ麦の色でもありますが、「思い慕う」という意味の方にもとれます。麦から焦げたような匂いも感じるような、遠くさすらうような気持ち。すっきりとした詠み口ながら、心に響いてくる句です。
戦野いま卍巴の麦の波 まゆみ
画像をクリックすると、画像が拡大されます。

穂麦は「焦がるる」ような色。
※写真や文章を転載される場合は、お手数ですが、お問い合わせフォームから三和書籍までご連絡ください。